プログラム
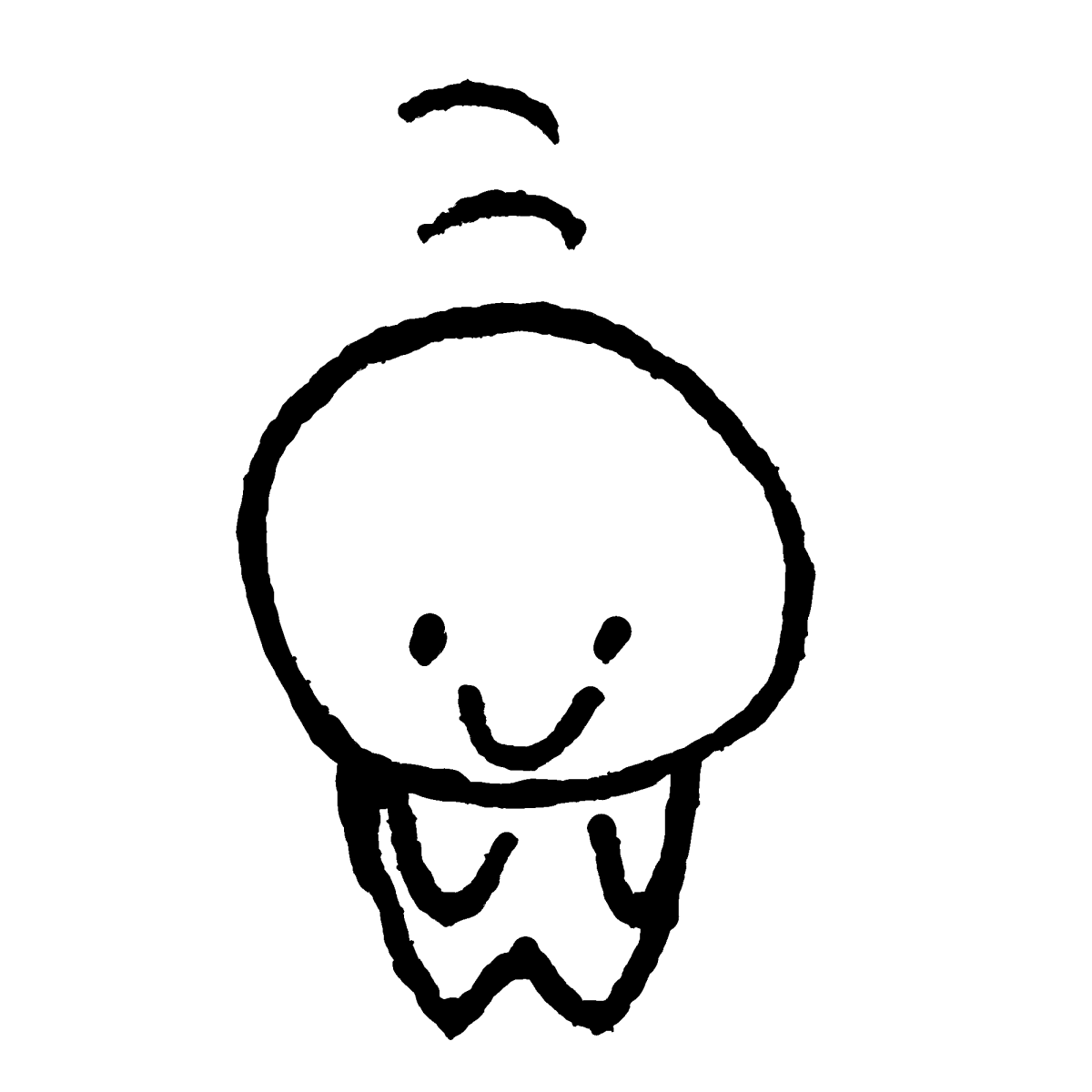
抄録集公開(12/27更新)!!
日程表が最新版になりました(12/26更新)!!
理学療法教育ガイドライン委員会企画
『理学療法教育ガイドライン0版』先行公開!!
口述・ポスター発表の演題公開!!
下のボタンからダウロードできますよ。
講演・シンポジウム
大会長基調講演
1/10(土)10:00~11:00 第1会場
日本理学療法教育学会の未来~今こそ叡智を集約せよ~
〇講師:芳野 純(第14回日本理学療法教育学会学術大会大会長:帝京平成大学)
〇座長:高木 亮輔(JA静岡厚生連 中伊豆温泉病院 通所リハビリテーション リハッピー)
特別講演
特別講演① 1/10(土)11:00~12:30 第1会場
医療者教育の理論と実践の往来の旅から見えてきた今の情景
〇講師:西城 卓也(岐阜大学医学教育開発研究センター)
〇座長:芳野 純(帝京平成大学)
特別講演② 1/10(土)14:00~15:30 第1会場
理学療法士養成課程学生の学習動機づけと教育的意義
~初年次の学習、臨床実習、国家試験の3局面からの考察~
〇講師:成田 亜希(宝塚医療大学)
〇座長:池田 耕二(奈良学園大学)
特別講演③ 1/11(日)13:20~14:50 第1会場
理学療法士のキャリア形成を考える
~「人生100年時代」のキャリア自律と教育者の役割~
〇講師:松本 泉(株式会社シーユーシー)
〇座長:岩﨑 裕子 ( YMCA米子医療福祉専門学校)
シンポジウム
1/10(土)15:50~17:50 第1会場
「ガイドライン改正後の診療参加型臨床実習とその後の教育効果」
〇座長:薄 直宏(東京女子医科大学附属八千代医療センター)
〇講師:落合 慶之(関西総合リハビリテーション専門学校)・・・学校教育から
:上倉 洋人(志村大宮病院・茨城北西総合リハビリテーションセンター)・・・卒後も担う臨床実習の現場から
:木村 大輔(川崎医療福祉大学)・・・卒後教育から
ランチョンセミナー
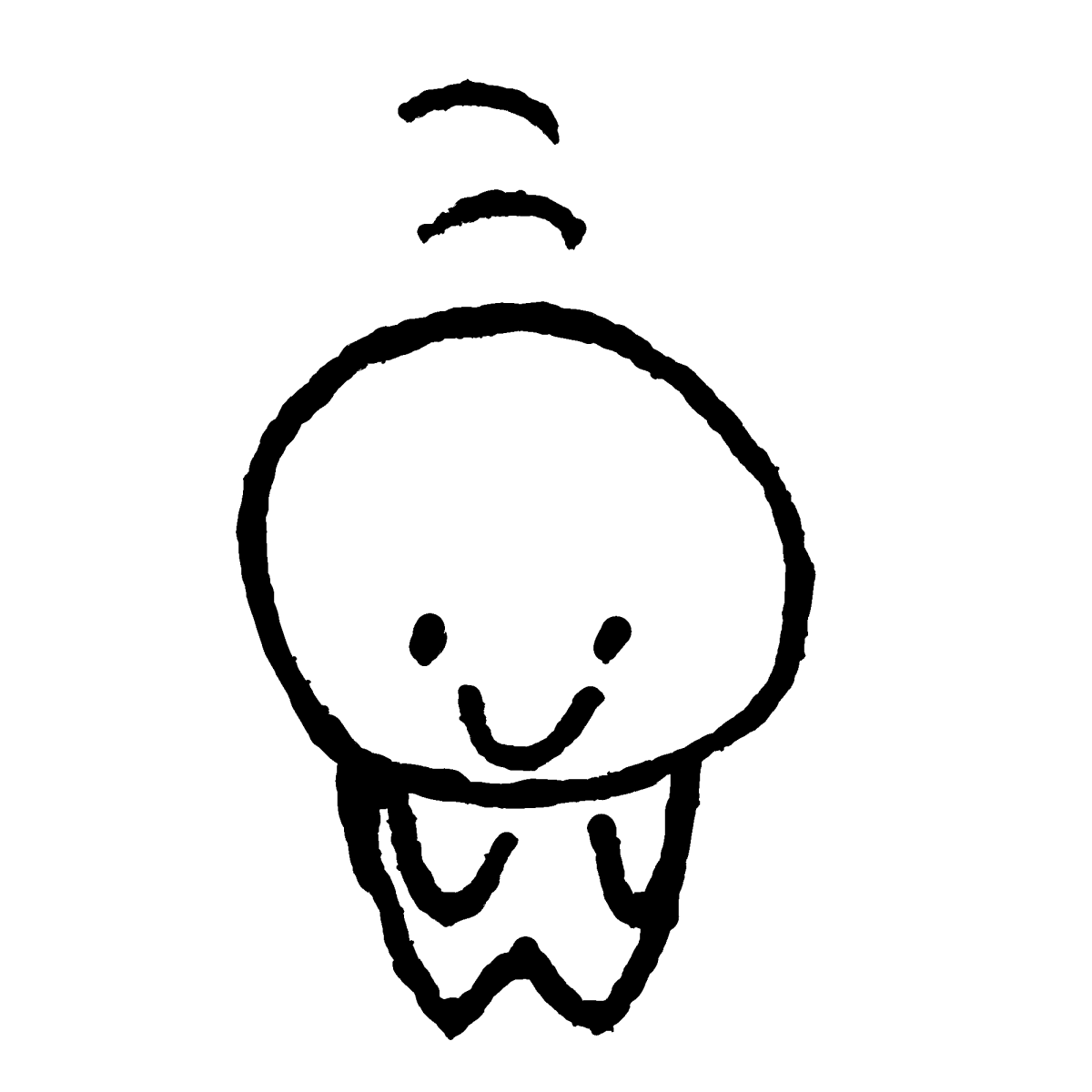
*当日の朝チケットを配布します(各日100名)詳細は「参加者へのご案内」に掲載予定
ランチョンセミナー①
1/10(土)12:40~13:40 第2会場
「明日から使える!生成AIで変わる理学療法教育:症例検討・レポート指導・院内研修資料作成の実演デモ」
〇講師:福谷 直人
〇共催:バックテック株式会社
ランチョンセミナー②
1/11(日)12:00~13:00 第1会場
「理学療法教育におけるICT活用の取り組み・効果・展望」
〇講師:桑江豊・深谷泰山
〇共催:エスエイティーティー株式会社
公募型
当日参加OKですが、、、
定員もありますので、ぜひ事前参加申し込みしてくださいね!!
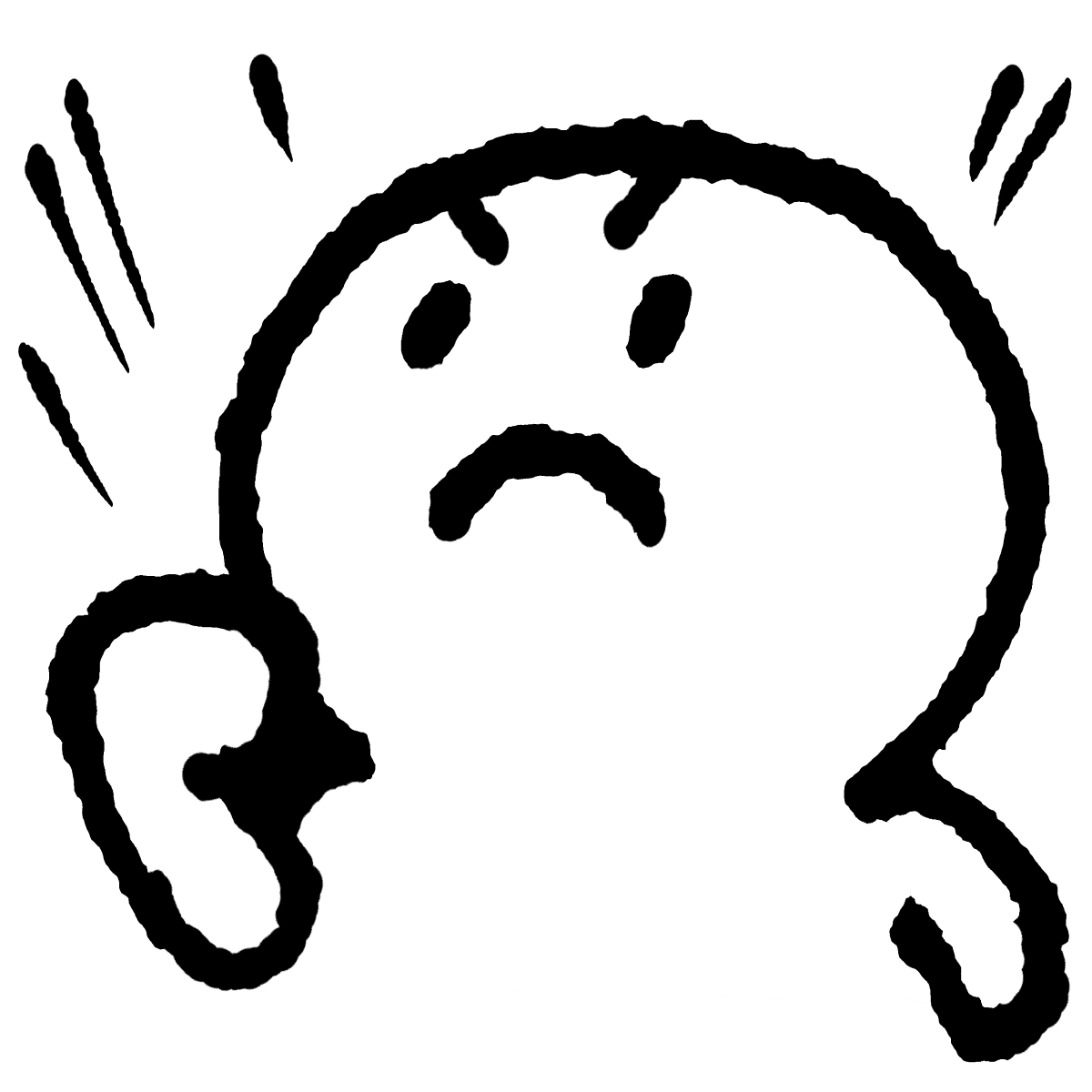
公募型日程表
1月10日(土) 14:00~15:30
公募型① 第4会場‐① シンポジウム 代表:久保 大輔
『臨床現場におけるEvidence-based Practice教育の課題と実践
―EBP教育の組織的支援の可能性―』
公募型② 第4会場‐② ワークショップ 代表:森本 智栄
『転職時代における人材育成 – 定着と成長の新しいバランス -』
1月10日(土) 16:10~17:40
公募型③ 第3会場‐① ワークショップ 代表:児玉 慎吾
『協働学習で、学習者は何を学び、教育者はどのように支援するか
-Small Group Learningの体験学習から学ぼう-』
公募型④ 第3会場‐② ワークショップ 代表:奥野 将太
『モチベーションをデザインするARCSモデルのすすめ』
公募型⑤ 第4会場‐① シンポジウム 代表:森 明子
『ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法学の教育と実践:現在の取り組みと今後の課題』
公募型⑥ 第4会場‐② ワークショップ 代表:酒井 直樹
『教育にコーチングを使用して「なりたい自分」への伴走』
1月11日(日) 10:00~11:30
公募型⑦ 第4会場‐① シンポジウム 代表:玉利 誠
『主体的な学びを促進する教育デザイン〜心理的要因からAI活用まで〜』
公募型⑧ 第4会場‐② ワークショップ 代表:海老原 賢人
『学びの“個性”を活かす!〜自己調整学習で拓く、医療専門職の生涯学習〜』
1月11日(日) 13:20~14:50
公募型⑨ 第3会場‐① ワークショップ 代表:堀 寛史
『臨床推論を深めるための統合と解釈文章作成の実践』
公募型⑩ 第3会場‐② ワークショップ 代表:松本 渉
『教える難しさと向き合う~臨床現場における指導のリアル~』
公募型⑪ 第4会場‐① シンポジウム 代表:善明 雄太
『教える側を育てるということ 〜教育と臨床をつなぐ“教える文化”の再構築〜』
公募型⑫ 第4会場‐② ワークショップ 代表:吉澤 悠喜
『臨床を”振り返る力”を育てる!-三角ロジックを活用した指導法の体験-』
公募型ワークショップ詳細
公募型② 1/10(土)14:00~15:30 第4会場‐②
『転職時代における人材育成 – 定着と成長の新しいバランス -』
〇森本 智栄(帝塚山リハビリテーション病院)
定員20名
- ワークショップ要旨
-
転職が当たり前となった現代において、理学療法士の人材育成を再検討します。転職を単なる人材流出と捉えるのではなく、個々の成長と組織の発展の好機と前向きに捉えます。短期間での実践的スキルの習得や汎用的な能力の育成、多様なキャリア支援、ネットワーク形成、魅力的な組織文化づくりなど、持続可能な仕組みについて、参加者と共に考え、悩みながら模索し、それぞれの現場に即した実践的な方向性を探ります。
- 紹介動画
-
公募型③ 1/10(土) 16:10~17:40 第3会場‐①
『協働学習で、学習者は何を学び、教育者はどのように支援するか-Small Group Learning の体験学習から学ぼう-』
〇児玉 慎吾(介護老人保健施設 恵風苑)
定員30名
- ワークショップ要旨
-
本ワークショップでは、参加者が、教育者として、協働のスキルを伸ばす「協働学習」の支援方法について、自身の活動の振り返りや参加者同士の対話から学び、明日からの実践に生かせることを学習目標にしています。
また、グループワークでの協働学習を通し、「自己主導的な学習態度・方法」「協働のスキル」を省察し、その場にいる人が持つ「多彩な叡智」を集結できる時間・空間・関係を創る工夫(仕掛け)を取り入れます。
- 紹介動画
-
公募型④ 1/10(土) 16:10~17:40 第3会場‐②
『モチベーションをデザインする ARCS モデルのすすめ』
〇奥野 将太(飯塚病院)
定員20名
- ワークショップ要旨
-
本ワークショップでは、学習者のモチベーションをデザインするARCSモデルを体験的に学びます。理学療法教育における具体的な場面を想定し、参加者同士のグループワークを通じて、教育効果を高めるための動機づけ戦略を考案・共有します。講義と演習を通して、教育現場で即実践できるスキルを習得し、学習者の意欲を高める教育者としての力量向上を目指します。
- 紹介動画
-
公募型⑥ 1/10(土) 16:10~17:40 第4会場‐②
『教育にコーチングを使用して「なりたい自分」への伴走』
〇酒井 直樹(おかたに病院)
定員20名
- ワークショップ要旨
-
本ワークショップでは、対話を通じて相手の想いや課題を整理し、「なりたい自分」に向かって歩むプロセスを支援する手法として、コーチングを紹介します。目的は、自ら考え行動する自律性を育むことにあり、コーチングはそのための有効な手段の一つです。体験的なワークを通じて、若手・ベテラン問わず、対話を深める関わり方を学び、安心して挑戦できる関係性づくりと指導の新たな可能性を探っていきます。
- 紹介動画
-
公募型⑧ 1/11(日) 10:00~11:30 第4会場‐②
『学びの“個性”を活かす!〜自己調整学習で拓く、医療専門職の生涯学習〜』
〇海老原 賢人(上尾中央医療専門学校)
定員30名
- ワークショップ要旨
-
医療専門職は、日々変容する社会的ニーズに対応するため、生涯にわたり学習を継続することが求められる。
自己調整学習とは、「学習者が、メタ認知・動機・行動の観点から、学習プロセスに能動的に参加する学習」と定義されており、医療専門職教育の現場にも理論体系
が導入されつつある。
「理学療法士の自己調整学習方略尺度」を活用し、学習者ごとの学びの“個性”を明らかにすることで、生涯学習について再考する機会としたい。
- 紹介スライド
- 紹介動画
-
公募型⑨ 1/11(日) 13:20~14:50 第3会場‐①
『臨床推論を深めるための統合と解釈文章作成の実践』
〇堀 寛史(甲南女子大学)
定員40名
- ワークショップ要旨
-
WS では、評価結果の相互関係を明確化し、臨床推論と結びつけて言語化するプロセスに焦点を当て、客観的データと主観的観察の統合・解釈力を強化し、根拠に基づく文章作成を学びます。また、WS は教育の現場での応用的指導法を提供し、学習者の批判的思考や問題解決能力の育成にも寄与することを目指します。多面的視点から評価内容を深く捉える力は実践的かつ教育的価値が高く、指導者や学習者双方のスキルアップに直結します。
- 紹介動画
-
公募型⑩ 1/11(日)13:20~14:50 第3会場‐②
『教える難しさと向き合う~臨床現場における指導のリアル~』
〇松本 渉(LE 在宅・施設 訪問看護リハビリステーション)
定員30名
- ワークショップ要旨
-
はじめに)働き方改革やハラスメント対策で、部下への指導は年々難しくなってきている。
目的)臨床でも度々」経験する教育の難しさに」ついて、他施設の療法士と共有し対話を行うことで、越境学習の機会とし、臨床教育者としての知見を広げる。
方法)①なぜ勉強しないといけないか②臨床教育をどこまで教えるのが職場の責務なのかの2点について、問題意識の共有を図った後、グループディスカッションを行いその成果を発表する。
- 紹介動画
-
公募型⑫ 1/11(日)13:20~14:50 第4会場‐②
『臨床を”振り返る力”を育てる!-三角ロジックを活用した指導法の体験-』
〇吉澤 悠喜(赤穂中央病院)
定員20名
- ワークショップ要旨
-
臨床実習生や若手臨床家をどう指導すれば、臨床を振り返る力が育つのか―そんな悩みを抱えたことはありませんか?本ワークショップでは、臨床の振り返りに活用できるフレームワーク「三角ロジック」の概要をミニレクチャーで学んだ後、臨床教育を想定したシナリオ演習を通して、学習者をどう導くべきかを考えます。ともに、より良い指導のあり方を考えていきましょう!
※定員を超えた場合は後方席での見学のみも可
公募型シンポジウム詳細
公募型① 1/10(土) 14:00~15:30 第4会場‐①
『臨床現場における Evidence-based Practice 教育の課題と実践
―EBP 教育の組織的支援の可能性―』
〇久保 大輔(横浜市立大学大学院)
- シンポジウム要旨
-
エビデンスに基づいた実践(EBP)は、質の高い理学療法の提供するための重要な概念である。しかし、EBPの教育機会は個人の意欲や各施設の状況(時間・リソースの不足等)によって十分に確保できていない。本シンポジウムは、急性期・回復期病院、作業療法分野、大学教員が具体的なEBP教育の事例や課題を共有し、参加者を含めた議論を通して各施設で導入可能なアイデアや方法論を検討する機会を提供することを目指す。
公募型⑤ 1/10(土) 16:10~17:40 第4会場‐①
『ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法学の教育と実践:現在の取
り組みと今後の課題』
〇森 明子(兵庫医科大学)
- シンポジウム要旨
-
ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法学は、骨盤底機能障害、産前産後ケア、前立腺全摘術後のリハビリテーション等を取り扱う領域である。日本では約43%の養成校で教育が行われているが、体系的なカリキュラムや臨床実習の機会は限定的である。本シンポジウムでは、現状と課題を整理し、教育の重要性と教育実践例を共有することで、本領域における理学療法士の専門性向上と今後の展望について議論する機会としたい。
公募型⑦ 1/11(日) 10:00~11:30 第4会場‐①
『主体的な学びを促進する教育デザイン〜心理的要因から AI 活用まで
〜』
〇玉利 誠(令和健康科学大学)
- シンポジウム要旨
-
2012 年中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて〜生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ〜」以降、高等教育においても主体的に学ぶ力の涵養が求められている。本シンポジウムでは、学習意欲に関係する心理的要因、学業的援助要請、協同学習、AI を活用した学習支援の可能性など、教育心理学と教育工学の視点から、主体的な学びを促進する理学療法教育について議論する。
公募型⑪ 1/11(日)13:20~14:50 第4会場‐①
『教える側を育てるということ 〜教育と臨床をつなぐ“教える文化”
の再構築〜』
〇善明 雄太(福岡脊椎クリニック)
- シンポジウム要旨
-
近年、理学療法士の育成には知識・技術の伝達だけでなく、「教える側」を育てる視点が不可欠となっています。良い組織を作るためには、健全な教育文化やシステムの構築が必須です。本シンポジウムでは、養成校教育者・臨床現場教育者双方の立場から、理学療法士育成の質を支える仕組みを問い直し、卒前・卒後教育の連携において必要な部分を再構築します。
本発表では、以下の五つの視点を軸に議論を展開します。
1.教育的スキル向上に向けた支援
教える 側には知識や技術を教える能力に加え、学習者の多様性を理解し、自己効力感を高めるよう支援する態度が求められます。そのための研修・コーチング体制、サポートや振り返りの仕組みを検討します。
2.卒前、卒後1〜3年目の成長曲線の捉え直し
新人期から中堅へ歩む過程を分析し 、成長パターンやつまずきの時期を提示します。学習者の発達段階を踏まえた指導が必要であり、教育者には適切な観察力と伴走の姿勢が求められます。
3.育てたい理学療法士像の共有
組織内で理想像を明示し、教える側と教わる側がその像を共有できるようなビジョン設計や合意形成を論じます。その際、「教育の中心は学習者である」という視点を教える側が持ち、主体的な学びを促す姿勢を持つことの重要性を強調します。
4.教育する側の苦慮の共有
教育を担う立場にある者は、時間的制約、臨床業務との両立、学習者との関係性の調整など、多様な困難に直面しています。こうした「苦慮する状況」を共有し合うことは、教育の現場における孤立感を軽減し、相互支援の文化を育む上で重要です。
5.教える文化を根づかせる仕組みの構築
日常実践において自然に教える機会を設ける制度設計や、評価システムを通じた仕組みを提案します。これにより、学習者を中心に据えた教育文化を組織に根づかせます。
これらの視点を通じて、「教育現場」と「臨床現場」の間に橋をかけ、持続可能な育成体制の再設計を目指します。特に、教える側が学習者中心の教育体制を意識し重要視すること 、さらに教育を担う上での困難を共有できる環境を整えることは、理学療法士養成の質的向上にとって必要不可欠です。本シンポジウムでは、具体的な支援モデルや運用のヒントも紹介し、参加者と共に議論を深める契機としたいと考えています。
学生企画
1/10(土)14:00~15:30 第3会場
理学療法の未来を担う学生と共に考える
~理想の理学療法教育とは何か~
学習の当事者である学生に将来の夢や希望・教育の課題等を発信していただき、参加者(理学療法士)と理学療法教育の未来を語る企画。
現在の学生たちが未来の理学療法を創り上げていくという視点に立ち、養成校教員や臨床実習指導者がそれを支援できる教育のためには何が出来るかを考えられる企画を目指す。
日本理学療法教育学会 委員会企画
理学療法教育ガイドライン委員会企画
1/10(土)12:40~13:40 第3会場
日本理学療法教育学会版 理学療法教育ガイドライン意見交換会
〇玉利 誠(令和肩甲科学大学リハビリテーション学部)
〇磯邉 崇(昭和医科大学 横浜市北部病院)
〇吉澤 悠喜(赤穂中央病院)
〇都留 貴志(市立吹田市民病院)
〇中川 仁(星城大学リハビリテーション学院)
現在日本理学療法教育学会にて作成中の「理学療法教育ガイドライン 0 版」を先行公開!
学術大会1日目(1月10日)の委員会企画にて参加者とともに意見交換を行います。
ぜひご一読の上、理学療法教育ガイドライン委員会企画に参加してください。
学術事業委員会企画
1/11(日)10:00~11:30 第3会場
理学療法教育教育学会が提言する臨床実習前後評価の基軸
〇問題提起:大塚 圭(藤田医科大学)
〇臨床実習前の評価:山形哲行(社会医学技術学院)
〇臨床実習後の評価:善明雄太(福岡脊椎クリニック)
第13回学術大会企画「理学療法教育における実習前評価の再考に向けて」に引き続き、臨床実習前後評価について参加者とともに議論し、日本理学療法教育学会としてのコンセンサスを得ることを目的とする。
全体報告会
1/11(日)16:10~16:40 第1会場
2日目の最終の企画。学術大会内容と参加者の意見を基に全体を振り返る。学術大会を通して明確になった事や今後の課題・目指すべき方向性を示し今後の日本理学療法教育学会の活動につなげる。